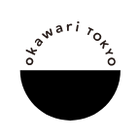Craftsman
Craftsman
海のミネラルバランスを<br>
そのまま塩に。<br>
こだわり抜いた塩の匠の技術
この塩をつくるのは、井上雄然(いのうえゆうぜん)さん。塩は身体を調える「調身料」の考えで、人が生まれた太古の海のミネラルバランスを目指した塩づくりをしています。

太古の昔、生命は海から誕生しました。当時の海水は塩分濃度が約1%と今より薄く、生物は体内に海と同じ体液をつくり、地上へ上陸することができました。実際に、私達の体液には約0.9%の濃度で塩分が溶け込んでいます。上陸したことにより、日々失われていくミネラルを補給するため、海水を煮詰め、体液のバランスを維持しようとしたことが、製塩の始まりです。

海水を汲み上げる山口県の油谷湾(ゆやわん)は、四方を森に囲まれた汽水域であり、周りの森は人の手が入っていない原生林が約80%も残っています。自然の生態系が残り植林に比べ植物の種類も多く、自然のミネラルを腐葉土に豊富に蓄えます。その森のミネラルが、雨とともに流れこみ、湾状の汽水域で海のミネラルと混ざりあいます。そうすることで、季節ごとのミネラルがたっぷりと含まれた味わい深い塩が生まれます。この地域は今では国定自然公園となっています。

汲み上げた海水を竹につたわせて少しづつ蒸発させることで、必要なミネラルを残しつつ濃度を高めていきます。また、最初から釜焚きをするのでなく、この工程を挟むことで、焚き時間を短縮し、CO2の排出も抑えられます。

濃縮した海水を予備焚きし、海水の濃度をささらに高めた後、釜に移して「本焚き」をします。約15時間目を離さず、塩の結晶になるまで焚き続ける作業。夏の本焚きは、灼熱の中行われます。また、薪を使って焚くことで火加減に差が生まれ、大粒・小粒が混ざり合った深みのある塩になります。

そして、一番重要なのは“天地返し”。塩に含まれるミネラルは、カルシウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウムなどそれぞれ 結晶化するタイミングが異なり、層になって焚き上がります。そのためまんべんなく天地を返しながら、各種ミネラル成分をまぜあわせることで、 太古の海のミネラルバランスを目指しています。

雄然さん曰く「塩屋の仕事は、マグネシウムを抜くこと」だそう。現在の海は、太古よりマグネシウムの量が約13倍に。そのため、杉樽を使い、不要な分のマグネシウムをにがりとして落とします。本来、海水に含まれる約87種の微量ミネラルは残しつつ、多分なものを抜くこの一手間で、身体に本来必要なミネラルバランスを活かした塩づくりを目指します。